
転職エージェントについて良く書いてある記事をたくさん見るのですが、これって本当ですか?転職エージェントにデメリットがないとは思えないのですが。考えすぎでしょうか?

こんにちわ、アドバイザーのくまさんです。私はキャリアアドバイザーとして、これまで多くの求職者と面談してきましたが、「転職エージェントの裏事情を知らないまま使って、結果的に転職活動に失敗した」「ようやく転職が決まったのに、実態が違いすぎてすぐに退職することになった」という声を聞いてきました。
このような事から一部のユーザーからは「転職エージェントは使わない方がいい」ですとか、悪いことは言わないから「転職エージェントはやめとけ」と言った意見が出ています。
そして、転職活動をする人は、いろいろな環境にいます。20代、30代で転職活動がうまく進まない方。また、40代、50代の方は求人数が減るだけでなく、さまざまな家庭環境(ex.子育てや親の介護等をしながら)によって、さらに転職活動が大変になります。たとえば親の介護がきっかけで退職をして、そのあとのブランク期間が長かったことにより転職活動がうまく行かなかった人も多数いらっしゃいます。
そこで本記事では、私が大手転職エージェントでキャリアアドバイザーをしていた時の、求職者から聞いたリアルな話しを紹介して、転職エージェントのデメリットの実態をお伝えします。
転職活動は、転職エージェントを利用した方がメリットが大きいです。「転職エージェントは便利」という情報だけを鵜呑みにするのではなく、「転職エージェントに潜む本当のこと」を理解し、最適なパートナーを選び転職活動をするようにしてください。
転職エージェントのデメリット、やめとけ、使わない方がいいと言われる理由とは
ビジネスモデルによる“急かし”プレッシャー
転職エージェントのビジネスモデルは、みなさんの転職が成功する(入社が決まる)と、求人企業から「年収の30~35%」をフィーとして受け取る仕組みになっています。成功報酬型であるがゆえに、キャリアアドバイザーには売上目標があり、「月間●名の入社を獲得する」というノルマが課せられています。

求職者のみなさんにとっては、「在宅ワークの有無」や「残業時間」などが気になるかもしれませんし、家庭の事情によって優先する事項があるかもしれません。一方のキャリアアドバイザーは売上を優先していることがあり、みなさんのそのような事情を無視することもあります。
内定が出やすい求人を紹介してくる
転職エージェントのビジネスモデルが「成果報酬」であるため、内定が出やすい求人を紹介することもあります。これは私の勤めていた転職エージェントでも見かけた事例です。たとえば書類選考のハードルがとても低かったり、面接が1回で終わるような求人案件ばかりを紹介するパターンです。ちなみにこのような求人企業は退職率も高い傾向にあるので注意が必要です。
規模の違いによる求人件数の偏り
転職エージェントの業界は、以下のように一部の「大手」「準大手」規模の転職エージェントと、大多数の「中小」規模の転職エージェントから成り立っています。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 大手転職エージェント | 業界全体の数%程度。求人数は数千~数万件あり、全国各地の求人を幅広く保有。 |
| 中小転職エージェント | 業界全体の95%以上。社員数が数名~10数名ほどで、保有する求人件数は数十~数百件程度。エリアや職種に特化しているケースも多い。 |
この規模の差が保有する求人数に比例をし、みなさんのニーズに合う求人を紹介できるかどうかに大きく影響します。たとえば子育てや親の介護をしている人ですと、大手転職エージェントでも「時短可」「在宅勤務可」の求人は保有求人全体の約10%程度。どうしても選択肢が限られてしまいます。できるだけ複数の転職エージェントに登録して、求人案件を増やす方にした方が良いでしょう。
キャリアアドバイザーの実力差が招く“ミスマッチ”
同じ会社でも、キャリアアドバイザーの実力は千差万別です。これはみなさんの会社でも同じで、社内の人材の実力は均一ではありませんよね。以下のような理由で、担当となるキャリアアドバイザーを見誤るとミスマッチが起こりやすくなりますのでご注意ください。
①業界・職種知識の乏しいキャリアアドバイザー
業界経験が無い求人案件を、その業界経験者に紹介するパターン。たとえばサービス業出身のキャリアアドバイザーは、ある程度勉強はしているものの当然ながらITエンジニアや製造業の求人について深くは理解していません。専門用語などについてかろうじで理解しているだけで、実態について理解していないキャリアアドバイザーが多いのです。じつはこのようなケースは非常に多いため、このようなキャリアアドバイザーがみなさんの今後のキャリアを見通すことは不可能です。
②転職成功体験がないキャリアアドバイザー
そもそもキャリアアドバイザーのなかには、転職を経験していない、もしくは転職を繰り返し失敗した、といった人が多かったりします。つまり「自分自身の成功体験に基づく説得力のあるアドバイス」ができない人も多いのです。
③ビジネスマナーがひどい担当者
社会人としての教育や経験が不足しているせいなのか、ビジネスマナーもダメで、かつ上から目線で求人案件を紹介するようなキャリアアドバイザーがいます。キャリアアドバイザーは求職者に頼られる仕事。そしてたくさんの求職者に頼られることで、自分は偉い、すごいといった勘違いするアドバイザーが多いのです。
こうなってしまうと、まともに転職アドバイスを聞く気持ちにもなれないことでしょう。
キャリアアドバイザーは経験が無くても、または国家資格を持っていなくても出来る仕事です。それゆえ個々の実力・レベル感が様々なのです。そのため、頼れるキャリアアドバイザーに出会うには、複数社の転職エージェントに登録をしてみるしかありません。
アドバイザーの実力差は「知らないまま進めると必ず後悔する」要因になります。以下の6パターンは要注意です。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 転職を繰り返している | 成功体験がなく、アドバイスに説得力を欠く |
| 未経験業界・職種を担当 | 自身が経験していない分野を担当している |
| 新入社員・若手 | 転職アドバイスの経験が少ない |
| 年下、かつ経験がない | 自分より年下で経験が足りないため、同じ目線に立てないタイプ |
| 上から目線 | 相談者に対して高圧的に感じられる話し方をする |
| ビジネスマナー不足 | 基本的なマナーができておらず、それゆえに信頼に欠けるタイプ |
求人数が少ないための失敗リスク
おもに40代、50代の方に対してのメッセージになります。40代、50代でさらにご家庭の事情(子育て、親の介護等)をお持ちの方については、“残業10時間以内”や“週3日在宅”など厳しい条件を付けると、求人件数は場合によっては数件にまで絞られてしまうことがあります。
このようなケースでも、やはりできるだけ複数の転職エージェントに登録して、求人案件を増やす方にした方が良いでしょう。
事前情報が違い“早期退職”を招くリスク
いざ内定をもらい希望の会社に入社できたと思っていても、入社後の実態が事前に聞いていた情報と違う場合があります。「時短はOKと言われたが、実際には所属部署の雰囲気で時短勤務がしづらい」「在宅勤務の割合が減らされ、結果的に介護に手が回らない」といった問題が起こるケースです。転職エージェント側のフォローが薄いと、せっかく入社した会社でも早期退職に追い込まれることがあるのです。
デメリット(=やめとけ、使わない方がいい)につながるケース
家庭の事情を正確に把握できないケース
親の介護をしている求職者の方の場合についてです。介護認定には「要支援1〜2」「要介護1〜5」がありますが、同じ「要介護2」でも、人によって必要なケア時間やサポート内容が大きく異なります。求人票に「介護制度あり」と書かれていても、実際にどこまで許容されるのかは企業によってバラバラ。
そのためキャリアアドバイザーへ今の介護負担の状況をできるだけ正確に伝えなければならないのですが、求職者も「何をどこまで伝えればいいのか」が分からず、一方のキャリアアドバイザーも介護についての理解が乏しく充分なヒアリングが出来ないことが多くあります。その結果、希望に合った求人に出会えないことがあるのです。
このようなケースは、たとえば子育てや親の介護を経験したキャリアアドバイザーでないと充分なフォローは出来ないでしょう。
複数エージェントを使いすぎるケース
これは転職エージェントというよりは、みなさん自身に問題があるケースです。転職活動の軸が定まっていないことが原因で、とにかく多くの求人案件を紹介してもらうことで安心感を得たいために、6社、7社と転職エージェントに登録してしまうのです。
そうすると、それぞれの転職エージェントから、いくつもの面談や面接日程の連絡が入ることで、求人案件の優先順位を決めることが出来なくなるといった本末転倒なことが起こることがあります。スケジュール調整が出来ずにせっかくの面接がキャンセルという事態にもなりかねません。
働きながらの転職活動の場合は限られた時間を有効活用しないといけません。このような利用方法では、情報が散乱するだけで大きなストレスになります。
紹介求人数が増えるケース
キャリアアドバイザーには売上目標が設定されているケースが多いのですが、設定される目標は売上だけでなく、「毎月○件の書類応募」→「月内○件の面接設定」→「○名内定」という数値目標(いわゆるKPI目標)が設定されていることが多くあります。
「書類応募数を増やせば内定が出る確率が上がる」という転職エージェント側の考えから、あなたの希望条件を無視して「とりあえず書類応募数を増やして内定を取りに行きましょう」と、とにかくたくさんの求人案件を紹介されて混乱してしまうケースがあります。

対策としては、応募先を自分で厳選する気持ちを持つことが重要です。ノルマ重視の転職エージェントは、みなさんのニーズに合うかどうかよりも「応募数と内定数」を優先するときもあります。そのような場合は「応募数ではなく、応募する企業の質を優先したいので、月3社程度に絞ってじっくり提案してほしい」と明言することをおすすめします。
デメリットを理解して「信頼できるエージェントを選ぶ」ポイント
転職エージェントのデメリットを理解したら、次は「どうすれば信頼できる転職エージェントを選べるのか」を具体的に解説します。以下の5つのチェックポイントを順番に確認し、介護転職において“失敗しない”エージェントを見極めましょう。
【チェック1】ニーズを深堀りする“質問力・ヒアリング力”があるか?
面談時に最低限、以下の3つの質問を投げかけてみてください。ここでは親の介護をしているケースで紹介します。
「貴社経由で入社した介護中の方は、実際に週何時間まで在宅勤務できたのか?」
「過去1年で、要介護2以上の方が何名内定し、実際に何名が現在も勤務を継続しているのか?」
「紹介企業で、介護休暇・休業の申請実績がある会社名とその取得可能期間を教えてください。」
上記の質問に対しての回答事例ごとの評価レベルを表にまとめました。
| 評価レベル | 回答例 |
|---|---|
| ◎ レベル | 数字で具体的な実績を挙げてくれる 例:「A社では昨年、介護中の方が3名在宅70%勤務を実現し、現在も継続中です」 |
| △ レベル | 曖昧な回答 例:「一般的には在宅勤務可能ですが、詳細は企業によって異なるため確認が必要です」 |
| × レベル | まったく具体性がない回答 例:「その情報はございません」「担当者から改めてご連絡します」 |
上記は「親の介護をしている求職者向け」の確認方法でしたが、基本的な質問・確認事項は他のみなさんも一緒です。ここでは「介護」をキーワードに質問をしていましたが、この「介護」の部分をみなさんの希望する条件に置きかえてみてください。
【チェック2】過去の転職サポートの実績について確認
過去の転職支援実績について確認してみるのも、そのキャリアアドバイザーの実力を見抜くのに役立ちます。
「〇〇社への転職支援をして、入社した人が何人いるか」と聞くことで、その方の今までの実績や経験が分かりますし、「入社後、何名くらいが今も勤務しているのでしょうか」と確認することで、求職者との距離感が分かります。求職者に寄り添うキャリアアドバイザーは、入社後の状況も確認することが多いのです。
このようにキャリアアドバイザーの実績を把握することで、みなさんへのサポートの期待値を図ることが出来るのです。
【チェック3】内定後の求人票とのギャップを埋める“フォロー力”があるか?
少し先の話しになります、いざみなさんが内定が出た後の話しです。
転職活動が成功したかどうかは、内定を獲得したかどうかではありません。転職活動の成功とは、入社したあとの会社生活なのです。
そこで重要なのが、キャリアアドバイザーによる内定獲得後のサポートです。たとえばみなさんが内定がでたら、「入社前の配属先訪問」や「(キャリアアドバイザーの)入社後のフォロー面談」といったサポートをしてくれるかです。
繰り返しになりますが、転職エージェントのビジネスモデルは「成果報酬」です。よって内定が出て入社が決まると、そのままフォローをしないキャリアアドバイザーも多いのです。しかし本当に親身なキャリアアドバイザーは、入社後のみなさんの様子も気にかけてくれるものなのです。
「入社前に配属先リーダーとの顔合わせをセッティングしています」
「入社後1ヵ月と3ヵ月のタイミングで状況をヒアリングし、入社前の条件と違うようであれば企業へ再交渉します」
このように入社後フォローが明確に約束されているかどうかを確認しましょう。曖昧な回答で終わるようであれば別の転職エージェントを検討するのがおすすめです。
【チェック4】キャリアアドバイザーの基本的な資質
キャリアアドバイザーが信頼できる人物かどうかは、あらためて会社員としての基本的行動が出来ているかを確認することも必要です。
1.対応速度
面談依頼や問い合わせメールへの返信が迅速に対応しているかどうか(24時間以内)。
2.敬語と丁寧さ
みなさんへの語りかけが、「〜様」と相手を敬い、「いつもお世話になっております」といった表現が適切に使われているかどうか。よくあるパターンは、求職者のみなさんの距離感を縮めたいのか、それともただマナーが無いのか分かりませんが、相槌を「うん、うん」と連呼するタイプです。以前勤めていた転職エージェントでもこのようなアドバイザーは多かったのですが、指摘しても結局治らなかった人が多いです。
3.家庭事情への配慮
たとえば「子育て」や「親の介護」といった求職者みなさんそれぞれの家庭事情について具体的にヒアリングしてくれるか。
このようにビジネスマナーと同時に、みなさんそれぞれの事情への配慮が見えるかどうかも重要な見極めポイントです。
【チェック5】大手・中小のどちらが自分に合うかを比較する
「大手転職エージェント」「中小転職エージェント」のどちらを選ぶか、または併用するかはとても重要なポイントになります。大手と中小にはそれぞれメリットもあればデメリットもあります。
【大手転職エージェント】
| メリット | 求人数が圧倒的に多く、業界や職種に特化した専門チームがある |
|---|---|
| デメリット | サポートが流れ作業になるときがある。新卒のキャリアアドバイザーもいる |
【中小転職エージェント】
| メリット | 地域に特化した求人を多く保有し、社長や採用担当者と長年の付き合いで親しいことが多く、そのため企業の文化や風土の理解の深さと交渉がスピーディーなことがある |
|---|---|
| デメリット | そもそもの求人数が少ない |
私のおすすめは、大都市近郊にお住まいの方については、求人数が多い大手エージェントを優先。地方にお住まいの方は、中小エージェントの地域密着型の強みと、出来れば大手の転職エージェントへの登録も推奨します。詳しくは以下の記事で特集をしています。
厳しい環境のなか、転職を成功させた二人の実話
以下のお二人は、私が転職エージェントのキャリアアドバイザーをしていた時に、同僚から聞いた実話になります。お二人に共通していたのが、ともに「親の介護」をしながらの転職活動だったこと。つまり、今後の働き方も「親の介護」は必至であり、そのような働き方を容認してくれる会社を選ばないといけませんでした。またお二人ともミドル世代で、20代・30代の方と比べると求人数が多くはありませんでした。
【実話その1】ママ美さんがつかんだ“理想の働き方”とは?
ママ美さんは、最初のキャリアアドバイザーとの面談で伝え方が悪かったのか、家庭事情を十分に理解してもらえませんでした。その失敗を経て「今の介護の現状が分かるシート」を面談前に提出するようにしました。別のエージェントの担当アドバイザーEさんに資料を渡したところ、Eさんは「これは助かります」と即座に反応し、求人企業側ともすぐに調整を始めてくれたのです。
たとえば、「在宅率50%・残業月10時間以内を希望」という求人案件を探してもらい、最終的には「オンライン会議中心で在宅勤務が多く、デイサービス送迎の時間帯は出社不要」という条件で内定を獲得しました。現在は週2日の出社、あとは自宅で働くスタイルを実現しました。母親のデイサービス送迎も無理なく続けられ「転職エージェントに時間と情報を正確に伝えたこと」により、理想の結果になったようです。
【実話その2】パパ夫さんが経験した“失敗からの再スタート”ストーリー
パパ夫さんは一度中小エージェントB社で転職活動をしたもののうまく進まず、その後大手エージェントC社に登録し直しました。C社では最初の面談で「介護の状況」と「気になる質問」をメモにまとめて、いくつかの質問を投げたそうです。
その結果キャリアアドバイザーから「介護中の社員が在宅50%勤務を実現している企業名と人数」「入社後の時短勤務申請が通った事例数」「要介護2でも入社可能な職種と現場の声」などを具体的に教えてもらったそうです。
「このアドバイザーなら間違いない」と確信でき、その後はそのキャリアドバイザーを信頼してに二人三脚で転職活動を続けたそうです。そしてついに、介護休暇制度が整った中小企業F社から内定を獲得。現在は父親のリハビリ送迎に付き添いつつ、週3日在宅+出社2日(残業ゼロ)という働き方を実現しています。
家庭事情(介護)×転職で大切にしたい“心構え”
1.家庭事情(介護スケジュール等)を可視化する
今の家庭事情について具体的に「何曜日の何時に何をしているか等」を明示するようにしましょう。これがあるとキャリアアドバイザーも具体的な求人案件を探しやすくなります。
2.自分から求人票や現場情報を徹底確認する
たとえば「求人票に介護OK」と書かれていても注意が必要です。必ず「実際には何時間在宅したのか」「残業時間は実際にどれくらいか」など、数字や事例を確認するようにしてください
3.ミスマッチを早期に認識したら速やかに軌道修正する
面談時に「この求人は今の自分にはちょっと違うかも」と思ったら、必ずその場で確認することで、新しい求人案件を紹介してもらえるかもしれません。とにかく「もやもやを放置しない」ことが転職活動の成功のコツになります。
まとめ―デメリットを理解すると、やめとけ、使わない方がいいは無くなります
それでは本記事についてのまとめをもう一度確認します。
転職エージェントのデメリット
・ビジネスモデルゆえの急かしプレッシャー
・エージェント規模による求人件数の偏り
・キャリアアドバイザー実力差によるミスマッチ
・求人件数が偏ることで選択肢が狭まる問題
・入社後フォロー不足で早期退職に追い込まれるリスク
信頼できるエージェントを見極める5つのチェックポイント
・質問力・ヒアリング力があるか
・過去の介護者サポート実績があるか
・求人票と現場のギャップを埋めるフォロー体制があるか
・担当者のビジネスマナーは適切か
・大手・中小どちらが自分に合うかを見極める

家庭事情を抱えながら転職活動をするのは、想像以上にハードルが高いものです。しかし、「デメリットを知らずに使う」「担当者やエージェントの選び方が甘い」という小さな失敗を防ぐだけで、転職成功率は大きく変わります。この記事で紹介したノウハウをフル活用し、エージェントと二人三脚で進めてくださいね。応援しています。
【著者情報】くまさん(介護と転職のアドバイザー)
| 年齢 | 在籍期間 | 在籍企業 |
|---|---|---|
| 22~34歳 | 10年 | 金融機関勤務(大手銀行、米系証券会社) |
| 35~45歳 | 10年 | 大手転職エージェント |
| 45~50歳 | 5年 | 介護系ベンチャー企業 |
| 50歳~ | 5年以上 | 独立して介護と仕事のコンサルタント |
| 年 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1970年 | 0歳 | 神奈川県横浜市に生まれる。 |
| 1992年 | 22歳 | 大学卒業後、みずほ銀行に入行(法人営業担当)。 |
| 2000年 | 30歳 | 米系証券会社に転職し、主に債券を扱うトレーダーを行う。 |
| 2005年 | 35歳 | 大手転職エージェントにキャリアチェンジ(ミドル層の転職支援)。広告やプロモーション全部門の責任者となる。またキャリアアドバイザーとしての経験もあり、求職者のお気持ちに寄り添うカウンセリングを得意とした。 |
| 2015年 | 45歳 | IPO直前の介護ベンチャー企業に転職し、介護事業者の収益改善コンサルティングに従事。特養、訪問介護、通所介護、または有料老人ホームの経営や人事コンサルタント業務を行う。また、一般ユーザー向けには介護の相談窓口サービスを提供し、とくに仕事と介護の両立に悩む会社員をサポートしてきた。 |
| 2020年 | 50歳 | 独立し「Dr.介護と仕事のアドバイザー」として企業制度設計や講演、情報発信を開始。その流れで本ブログを執筆中。現在に至る。 |
| No. | 得意分野 |
|---|---|
| 1 | 介護と仕事の両立支援(一般ユーザー向け) |
| 2 | ミドル・シニア層(30代~50代)のキャリア再構築・転職支援(一般ユーザー向け) |
| 3 | 介護人材の採用・定着(介護事業者向け) |
| 4 | 介護事業者の経営支援(介護事業者向け) |
| 5 | ダイバーシティ経営(介護離職防止)(介護事業者向け) |
| 6 | 施設(老人ホーム)選びのアドバイス(一般ユーザー向け) |
| 7 | 50代以降のキャリア再デザイン(一般ユーザー向け) |
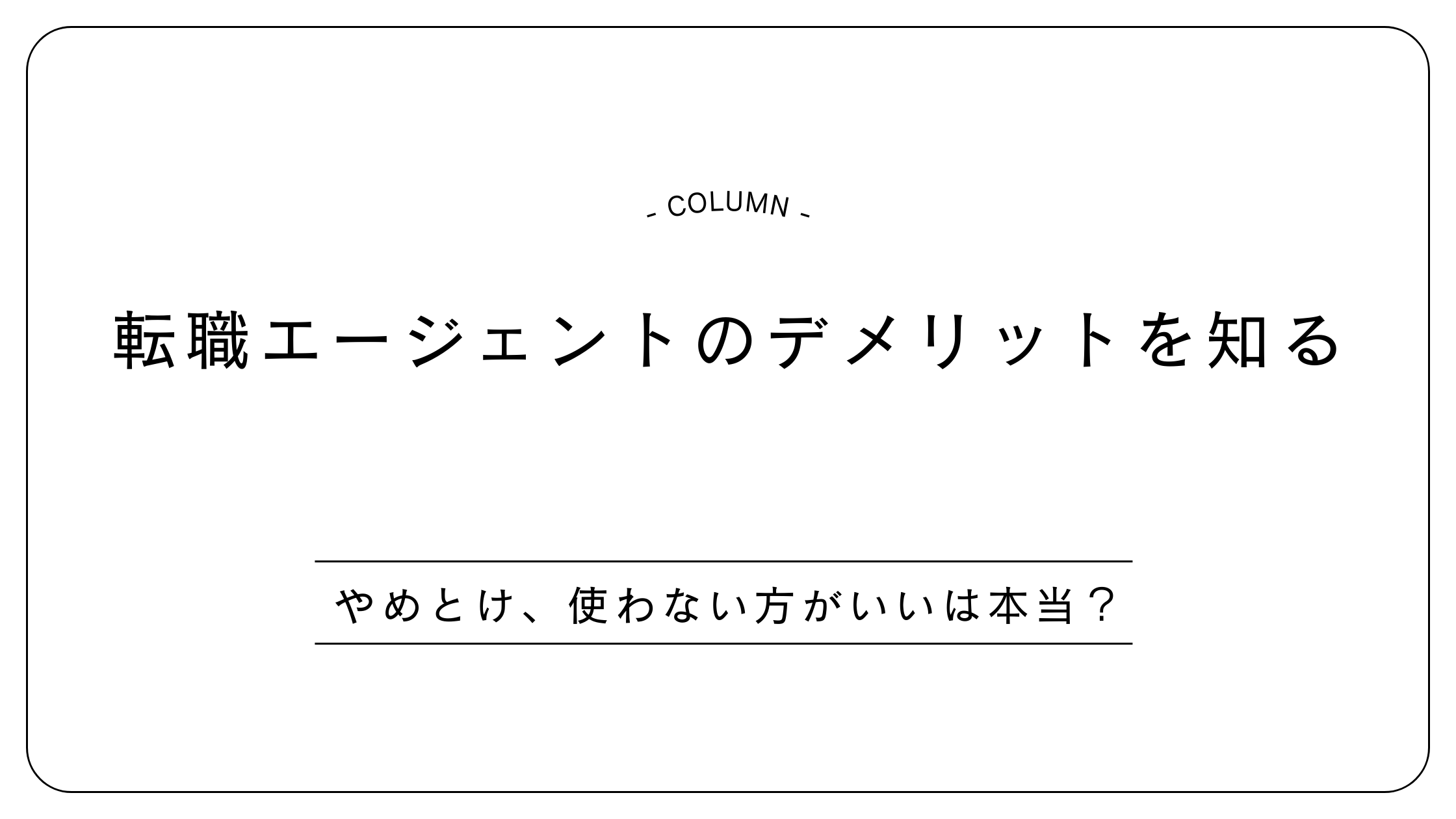


47歳のママ美さんは、都内のIT企業でマーケティング担当をしながら、実母(70代)の介護を続けていました。しかし最近では母親が週3回デイサービスを利用し始め、夕方5時には帰宅しますので時差出勤で対応するように。しかし会社に親の介護についてあまり理解してもらっていないと感じ、情報収集もかねて転職エージェントの利用を開始。ところが、登録した大手エージェントの担当アドバイザーはあまりこちらの意見を聞くことなく、一方的に求人案件を進めてきます。とにかく次から次へと求人を紹介するのです。「こちらの求人は時短勤務や時差出勤は可能なのですか?」「介護に対する企業姿勢はどうなんでしょう?福利厚生とか?」と聞いてみても、はっきりとした返事はありません。結果として、紹介された求人案件は、どれも納得が出来ずに転職活動が進むことはありませんでした。