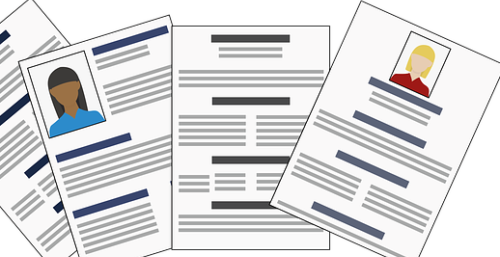老人ホームの入居の手続きをするとき、よく聞くのが「保証人」という言葉。
保証人と聞くと、ちょっと身構えてしまうかもしれません。そして保証人にはいくつかの種類があり、選び方や手続きでつまづく方も少なくありません。
本記事では、みなさんのリアルな疑問を交えながら、アドバイザーのくまさんが老人ホームにおける保証人についてやさしく解説します。

この記事を読めば、「保証人って何?」「どうやって選べばいい?」「費用やトラブルは?」といった疑問がすっきり解消。安心して老人ホームへの一歩を踏み出せますよ!
老人ホームの保証人とは?

最近、母が老人ホームへの入居を考えているんですが、見学に行った施設の担当者から『保証人をお願いできますか?』と言われて戸惑ってしまって。そのときしっかりと確認をすればよかったのですが、くわしいことを聞けなくて。そもそも保証人って、具体的にどんな役割を果たす人なんでしょうか?

いい質問ですね、パパ夫さん。保証人というのは、入居者さん自身が経済的に支払いできない場合に備えて、代わりに費用を負担する責任を持つ方です。ちょっと身構えてしまう話しかもしれませんが。入居者のご家族や親せきがなることが一般的ですが、その役割を詳しく見ていきましょう。
保証人って?
保証人とは、契約上の「支払い義務」を肩代わりできる人で、主に以下の2つの役割があります。
- 金銭的保証:家賃や食費、介護サービス料などの未払金を立て替え、施設に安心感を提供します。
- 身元確認:緊急時の連絡先として、入居者の安否確認や面会対応などにも関わります。
このように保証人がいることで、老人ホームは経営リスクを減らしつつ、高齢者の生活をしっかりサポートできる体制を築いています。
身元保証人・身元引受人・連帯保証人の違い

くまさん、先日見学した施設では『身元保証人と連帯保証人、どちらかをご用意ください』と言われました。でも、この2つの違いがよく分からず……。もし何かあったときに、どこまで責任を持てばいいのか心配です。

ママ美さん、そのお気持ちよくわかります。身元保証人、身元引受人、連帯保証人は名前が似ていますが、法的な責任範囲やサポート内容に大きな違いがあります。いろいろ細かく見てみると言葉が違っていて混乱しますよね。それぞれの特徴を詳しくお伝えしますね。
保証人、引受人、それぞれの違い
- 身元保証人
役割:入居者の身元を保証し、必要に応じて連絡を取る
責任範囲:未払いが発生した場合に支払いを求められることもあるが、連帯保証人ほど強い義務はありません。 - 身元引受人
役割:身元保証に加え、入居者の日常生活のサポートや急病時の対応を約束
責任範囲:生活支援面も含め、より広範囲にわたるフォローが求められます。 - 連帯保証人
役割:入居者と同等に支払い義務を負い、施設は入居者と連帯保証人のどちらにも請求可能
責任範囲:支払い義務は非常に重く、入居者が支払えない場合は先に連帯保証人に請求されます。
このように、それぞれの保証人には「どこまで?」という責任の範囲に違いがあるため、施設の募集要項や契約書をよく確認しましょう。

身元保証人、連帯保証人、そして身元引受人はそれぞれ意味が違いますので、入居を検討する際には契約条項などをしっかりと確認しておいてください。
証人に求められる条件と選び方

自分は保証人になることは問題なく大丈夫なのですが、施設の人のお話しだと保証人は親族以外の人にもお願いできると聞きました。具体的にどんな条件をクリアしている人であれば、保証人になれるのでしょうか?また、本当に他の人でもOKなのですか?

結論から言いますと、保証人は親族以外でもなれます。保証人の条件は施設によって多少異なりますが、一般的には以下の3つがポイントです。事前に候補になりそうな方としっかり話し合っておくと安心ですよ。
条件は
- 年齢・居住地
成人で日本国内に安定した居住実績があり、連絡が取りやすい住所を有していること。 - 収入・職業
家賃や介護費用の立て替えが可能な安定収入があること。公務員や会社員、定期的な年金収入がある方が望ましい。 - 信用情報
過去に支払い遅延や自己破産歴などがないこと。施設は必要に応じて信用調査を行います。
選び方のポイント
- 家族や近親者を優先:緊急時の連絡やサポートがスムーズ。
- 親族が難しい場合:友人、知人、あるいは専門の保証会社の利用を検討。
- 事前の同意取得:保証人候補とは責任内容や手数料等について事前に詳細に話し合いましょう。
保証人になれない場合の対策と代替案

親戚から老人ホームに入居するのに保証人になってほしいと頼まれたんですが。そこはお子さんがいないので、私たちに頼んできたようです。他に保証人を頼めそうな人がいなくて困っているようです。老人ホームに入居するときって、どうしても保証人が必要なのですか?何かほかの方法はありませんか?

それはお困りですよね、ママ美さん。ママ美さんのようなケースはよく聞く話です。最近は保証人の代行サービスや保証会社の利用など、さまざまな代替案がありますので、ご自身の状況に合わせて選ぶと良いですよ。
代替案として
- 保証会社の利用
概要:専門の保証会社が保証人を代行。
メリット:自分で保証人探しをしなくてよく、手続きがスムーズ。
デメリット:月額家賃の約1%程度の手数料がかかる。 - 連帯保証人不要プラン
概要:追加料金(家賃の数%)を支払うことで、保証人が不要に。
メリット:手続きが簡単で、精神的負担が少ない。
デメリット:追加費用が発生。 - 身元引受人サービス
概要:契約や生活支援まで総合的に引き受ける業者を利用。
メリット:契約後のフォローも任せられる。
デメリット:プランによって料金が異なるため、事前確認が必要。 - 公的支援制度の活用
概要:自治体や社会福祉協議会の緊急保証制度を利用。
メリット:低所得者向けに無償または低額で利用可能。
デメリット:利用条件が厳しく、申請に時間がかかる場合がある。
保証人契約の手続きと注意点

気に入った施設がみつかって、ようやく親の入居先が決まりそうです。実際に契約するときには、どんな書類を揃えればいいのかな?あと、契約書のどこに注意すればトラブルを避けられるかも知りたいです。

事前に予備知識を入れておいて、準備がしっかりできれば安心ですよね。では、必要書類と契約書のチェックポイントを詳しくお伝えします。
書類や契約書のチェックポイント
必要書類一覧
- 住民票(入居者・保証人)
- 印鑑証明書(保証人)
- 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
契約書のチェックポイント
- 保証範囲:未払い金の全額保証か、一部保証かを明確に。
- 保証期間:入居期間中のみか、退去後の一定期間までかを確認。
- 解除条件:保証人変更や契約解除の条件が定められているか。
- 連絡方法:未払い時や緊急時の連絡先・手順が契約書に記載されているか。
契約前には必ず施設の担当者と面談し、不明点はその場で解消しましょう。書面に残してもらうことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 老人ホームの保証人は誰がなれるの?
- 原則、成人で日本在住かつ安定収入がある方。家族優先ですが、友人や保証会社も選択肢になります。
- Q2. 老人ホームの保証人になりたくないのですが、どうすればいいですか?
- 保証会社の利用、連帯保証人不要プラン、身元引受人サービスなど、お困りの状況に合わせた代替案を検討しましょう。
- Q3. 高齢者の保証人になる費用はいくらですか?
- 保証人になるだけなら無料の場合もありますが、保証会社利用時は月額家賃の約1%前後の手数料が一般的です。
- Q4. 老人ホームの保証人は、無職でもなれる?
- 原則として安定収入が求められますが、年金収入が十分にある場合は施設側と相談可能です。
- Q5. 保証人に関するトラブル事例にはどんなものがある?
-
- 入居者が長期入院で未払いが膨らみ、保証人が全額負担したケース。
- 保証人になかなか連絡がつかず、施設側と保証人間で責任の押し付け合いになったケース。
- 契約解除条件を確認せず、保証人変更ができずトラブルに発展したケース。
まとめ
- 保証人の役割は「支払いと身元の二重の安心担保」。
- 身元保証人・身元引受人・連帯保証人の違いを理解し、責任範囲に合った選択を。
- 条件と選び方は「年齢・収入・信用情報」を確認し、家族・保証会社など最適な候補を検討。
- 代替案(保証会社、不要プラン、引受人サービス、公的支援)を活用可能。
- 契約前の書類準備と契約書チェックでトラブル防止。

くまさんも皆さんの安心した老人ホームライフを応援しています!ご質問があればお気軽にどうぞ。
【著者情報】くまさん(介護と転職のアドバイザー)
| 年齢 | 在籍期間 | 在籍企業 |
|---|---|---|
| 22~34歳 | 10年 | 金融機関勤務(大手銀行、米系証券会社) |
| 35~45歳 | 10年 | 外資系大手転職エージェント |
| 45~50歳 | 5年 | 介護系ベンチャー企業 |
| 50歳~ | 5年以上 | 独立して介護と仕事のコンサルタント |
| 年 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1970年 | 0歳 | 神奈川県横浜市に生まれる。 |
| 1992年 | 22歳 | 大学卒業後、みずほ銀行に入行(法人営業担当)。 |
| 2000年 | 30歳 | 米系証券会社に転職し、主に株式、為替を扱うトレーダーを行う。 |
| 2005年 | 35歳 | 大手転職エージェントにキャリアチェンジ(ミドル層の転職支援)。キャリアアドバイザーとして求職者のお気持ちに寄り添うカウンセリングを得意とした。 |
| 2015年 | 45歳 | IPO直前の介護ベンチャー企業に転職し、介護事業者の収益改善コンサルティングに従事。有料老人ホームの経営や人事コンサルタント業務を行う。また、一般ユーザー向けには介護の相談窓口サービスを提供し、とくに仕事と介護の両立に悩む会社員をサポートしてきた。 |
| 2020年 | 50歳 | 独立し「Dr.介護と仕事のアドバイザー」として企業制度設計や講演、情報発信を開始。その流れで本ブログを執筆中。現在に至る。 |
| No. | 得意分野 |
|---|---|
| 1 | 介護と仕事の両立支援(一般ユーザー向け) |
| 2 | ミドル・シニア層(30代~50代)のキャリア再構築・転職支援(一般ユーザー向け) |
| 3 | 介護人材の採用・定着(介護事業者向け) |
| 4 | 介護事業者の経営支援(介護事業者向け) |
| 5 | ダイバーシティ経営(介護離職防止)(介護事業者向け) |
| 6 | 施設(老人ホーム)選びのアドバイス(一般ユーザー向け) |
| 7 | 50代以降のキャリア再デザイン(一般ユーザー向け) |