
実家の父の様子がちょっと心配なんです。先月帰省した時ですが、以前より怒りっぽくなっているのです。母に聞くと、最近は頑固で話しを聞かなくなってるし、先日はなんと黙って新車を契約してきてしまったようなのです。ひょっとしたらそろそろ介護が必要なのかもしれませんが、どこに相談すれば良いのでしょうか?

お正月や夏休みに帰省をしたとき、親の様子がどうやら変だぞ、と気づかれたご家族の方から相談を受けることがあります。ここで、どんなときに介護相談するべきか、どこに介護相談するべきかを紹介します。
毎日の業務に追われる中、親の介護相談をどう始めればいいか悩んでいませんか?
「どこに連絡すれば」「誰に相談すれば」「何を準備すれば」「会社には相談しづらい」等など。こうした不安が、あなたの一歩を止めているかもしれません。
本記事では、限られたスキマ時間を有効活用しつつ、夜間や土日も使える窓口選びから、相談前のチェックリスト、当日の進め方、そしてアフターケアまでを、40〜50代の働く会社員目線で丁寧にナビゲートします。

介護の多くは突然直面するものです。そんな時は早めの専門家への相談が、介護負担を軽減する第一歩になりますので、まずは相談先について勉強してみてください。
親の介護相談をするとき

わたしの義母が最近物忘れが多くなってるようです。今でもキッチンで

はい、もちろんです。介護に関するいろいろな悩みに対して、
①家族の様子が変わり心配
②けがや病気が原因で生活が一変
③介護者自身の負担が限界に近い
介護相談はどこに?24時間、無料、電話でも相談OK

仕事終わりに電話したいのですが、夜間に対応をしてくれるところはありますか?または土日に相談してくれる場所があると助かるのですが。

多くの相談窓口は平日に対応しているケースがほとんどです。また相談内容によって窓口が違ってきますので、それぞれの対応窓口でどのようなサービスを提供しているのかを確認するようにしましょう。
市区町村の公的窓口
- 地域包括支援センター
- 対象:おおむね65歳以上の方とその家族
- 内容:介護保険の申請手続き、ケアマネジャーの紹介、在宅介護の総合相談
- 費用:無料
- 対応時間:平日9:00~17:00(休日・夜間は不定期)
- 高齢福祉課(市役所・区役所)
- 対象:どなたでも
- 内容:介護保険制度の案内、各種助成・給付の手続きサポート
- 費用:無料
- 対応時間:平日9:00~17:00
- 社会福祉協議会
- 対象:地域住民
- 内容:介護や福祉サービスの相談、ボランティア紹介
- 費用:無料
- 対応時間:平日9:00~17:00(支所によっては土日含む/要確認)
民間の相談窓口
- 老人ホーム紹介センター
- 代表例:あいらいふ、みんかい、など
- 内容:希望条件に合わせた施設のご提案・見学同行・入居手続きサポート
- 費用:基本無料(施設側から紹介手数料を受け取る形)
- 対応時間:サービス会社によるが、多くは9:00~21:00/年中無休
- 在宅介護支援事業者(民間ケアマネジャー)
- 内容:介護計画の作成、有料相談プランあり
- 費用:初回は無料相談、その後の継続サポートは有料(月額数千円~)
- 対応時間:各社による(24時間対応プランを持つところも)
- オンライン・電話相談サービス
- 代表例:各種民間コールセンター
- 内容:専門スタッフによる24時間・365日対応の電話相談
- 費用:無料、または有料(保険加入時の月額サポート等)
公的機関 vs 民間機関:窓口一覧比較
| 窓口名 | 公・私 | 費用 | 対応時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 公的 | 無料 | 平日9:00~17:00 | ケアマネへの橋渡しまでワンストップで支援 |
| 市区町村 高齢福祉課 | 公的 | 無料 | 平日9:00~17:00 | 介護保険申請・助成手続きの窓口 |
| 社会福祉協議会 | 公的 | 無料 | 平日9:00~17:00(拠点により土日可) | ボランティア活動や福祉サービス情報の紹介 |
| あいらいふ・みんかいなど | 民間 | 無料※ | 9:00~21:00(年中無休) | 施設紹介手数料は施設負担 |
| 民間ケアマネジャー事業者 | 民間 | 無料~有料 | 会社による(24h対応プランあり) | 有料プランは訪問サポートや緊急時対応を含む |

介護相談窓口は複数ありますので、まずはお近くの市区町村窓口にお問い合わせの上、必要に応じて民間サービスも併用してください。親御さんの状況やご家族の生活リズムに合わせて、最適な窓口を選びましょう。

すみません、くまさん。うちの父のことなのですが、最近の様子を見ているとひょっとしたら認知症の気配があるのではと思っていました。

年々、認知症を患う人が増えていて、この増加数が社会課題にもなっていますよね。もしかしたら認知症ではと思われた際の連絡先は、各都道府県の窓口や地域包括支援センターで相談ができますので、そちらにお問い合わせをするようにしてください。
| 年 度 | 認知症高齢者数(万人) | 有病率(%) |
|---|---|---|
| 2012年(平成24年) | 462 | 15.0 |
| 2015年(平成27年) | 517 | 15.7 |
| 2020年(令和2年) | 602 | 17.2 |
| 2025年(令和7年) | 約700 | 約19.0 |
また、介護対象となった認知症ご本人の平均年齢は以下のとおりです。
| 区分 | 平均年齢 |
|---|---|
| 全体平均 | 81.3歳 |
| 男性平均 | 79.9歳 |
| 女性平均 | 82.0歳 |
会社の上司や人事に介護の相談ができない!?

子育てと違って、なぜか介護のことは会社に相談しづらいのです。

会社員の人にとっては、本来はまず相談したいのは会社の上司や人事などではないでしょうか。実際には会社には相談がしづらいという人が圧倒的に多いのです。
仕事と介護を両立するためには社内制度の活用が欠かせませんが、相談には次のような心理的・制度的ハードルがあります。会社に介護の相談をする人の割合は10%にも満たないというデータもあるのです。それではなぜそのようになるのかを紐解いてみましょう。
①会社側の理解不足:上司や人事が介護の実態を十分に理解しておらず、「上司に相談したが、介護の経験が無いからわからないと言われた」「そもそも相談窓口が無い」といった介護に対する理解の欠如や体制が整備されていないといった現状が、相談をしづらくしているようです。
②自分が感じてしまう罪悪感:介護負担が増えることで、上司や同僚へ迷惑をかけたくない気持ちから、本音を話しにくい。
③制度の壁:介護休業法・看護休暇制度はあるものの、社内規程に落とし込まれていない場合がある。

「どの部署に何を申請すればいいのか」「誰にどのように相談すればいいのか」がわからず、アクションが先延ばしに。こうしたハードルを一つずつクリアしていくために、次章で具体的な社内制度活用法を紹介します
知っておきたい2025年育児・介護休業法改正
ここが変わった、育児・介護休業法
①誰でも使える介護休暇になった!
・以前は「継続雇用6か月未満」の人が除外対象でしたが、今改正でほぼ全員が対象に。
・入社したばかりでも、親や配偶者の介護が必要になったらすぐ申請できます。
②“通算93日”の休業が分割して取れる
・要介護家族1名あたり通算93日間の介護休業が取得可能。
・「しばらくまとまった休みが必要」「短い休暇を何度か取りたい」どちらもOK。
③会社に言いづらくても大丈夫!相談窓口の設置義務化
・会社は必ず相談窓口を設置し、制度概要や手続きフローを教えてくれる体制を整備。
・「誰に何を相談すればいいか」が分かるので、まずは相談窓口へ連絡を。
④個別周知&意向確認で不安を減らす
・「介護が必要になりそう」と申告したら、会社から介護休業や給付金の情報が個別に案内されます。
・面談やメールで自分の希望を確認してもらえるので、遠慮なく不安や疑問を伝えましょう。
⑤40歳での先行案内で備えられる
・40歳になると、介護休業制度の説明を会社から必ず受けられます。
・まだ介護の予定がなくても、制度を知っておけば急な事態にも落ち着いて対応できます。
⑥テレワーク利用も“努力義務”に
・要介護家族がいる場合、テレワークを希望しやすい環境作りが会社の責任に。
・「出社が難しい」「もう1日家でケアしたい」というときは、遠慮せず上司に相談してみてください。

改正で“使いやすさ”が大幅アップ。まずは社内の相談窓口をチェックして、自分の権利をしっかり活用しましょう!
まず整理しましょう、3つのこと
相談前に最低限そろえておきたい情報を、優先順位付きで整理しましょう。
①要介護度・認定結果
・直近の認定結果と要介護度の更新予定
②家族構成・これまでの介護状況
・同居有無、支援者・支援頻度の実績
③相談で解決したいこと
・在宅継続/施設検討/認知症ケアの強化 など
これらを手元にまとめると、相談時間を最大限に活用でき、的確なアドバイスが得られやすくなります。

メモはスマホのメモアプリにまとめると、相談先でスマホ一つで確認できます。『一番聞きたいこと』には赤字や★印をつけておくのがおすすめです。
介護相談窓口センターと地域包括支援センター

じつは「介護相談」と検索した人の多くが、一緒に検索しているのが「介護相談窓口センター」と「地域包括支援センター」のようです。ここでこれらの簡単な説明をしてみます。
介護相談窓口センターは、高齢者やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護保険サービスだけでなく、医療・福祉・健康全般の相談をまとめて受け付ける総合窓口です。具体例としては「地域包括支援センター」や「高齢者相談センター」などが該当します。
地域包括支援センターの利用方法
①窓口の場所を確認:お住まいの市区町村役所ウェブサイトや広報誌で「地域包括支援センター」の所在地・連絡先をチェック。
②電話で予約:まずは電話で「相談したい」と伝え、希望日時を調整します。空きがあれば当日の飛び込み相談も可能な場合があります。
③必要書類を準備:健康保険証、要介護・要支援認定証の写し(お持ちであれば)。また家族構成や相談したい内容をメモにまとめておくとスムーズです。
④当日窓口で相談:面談ブースでケアマネジャーや保健師がヒアリング。必要に応じて訪問調査や他サービスの紹介まで手配してくれます。
⑤フォローアップ:相談後、サービス利用開始に向けた書類手続きや、数週間後の経過確認を電話や訪問でフォローしてくれます。
高齢者相談センターの利用方法
①問い合わせ先を確認:「高齢者相談センター」は名前が市区町村によって異なる場合もあるため、役所の福祉課窓口に電話して案内を受けましょう。
②予約または飛び込み相談:多くは予約制ですが、歩いて行って相談できるケースも。電話で事前に確認すると安心です。
③相談内容の整理:介護保険サービスの利用手順、医療・福祉制度の活用方法、地域のサポート体制 …など
④当日面談:社会福祉士や保健師が、複数の相談テーマを一度にヒアリング。必要に応じて地域内の専門機関を紹介してくれます。
⑤アフターフォロー:専門機関への橋渡しや、その後の状況確認を電話・訪問で行い、安心して暮らせる体制づくりをサポートします。

これら2つの窓口は、いずれも無料で利用でき、介護保険から医療・福祉まで幅広く相談に乗ってくれます。初めての方はまず電話予約をして、気になることをまとめておくと安心です。
まとめ&次にすべきアクション
3. 社内制度を活用 → 介護休業法・EAPの具体的手順
4. 事前準備で相談時間を最大化 → チェックリスト&PDF
5. 当日はシミュレーション通りに進行 → ヒアリング→提案→フォロー
6. ケーススタディで具体的イメージ → 数字と期間を明示
7. 夜間・土日対応サービスを活用 → 365日窓口を確保
8. 時間管理&セルフケア → フレックス/オンライン/メンタルケア
介護相談は“早めに、そして具体的に”。まずは小さな一歩を踏み出し、安心できるサポート体制を整えましょう!
おまけ:転職相談はだれにする?
介護の悩みがどうしても解決できずに、仕事にも影響が影響が出てしまうケースもあります。今の仕事を続けることが難しくなり、介護離職をしてしまう人も見受けられます。「時短勤務ができれば」「在宅勤務の回数がもう少し多ければ」といったような、もう少し環境が変われば仕事が続けられるのにといった悩みもあるようです。そんなときに転職相談すべき相手は誰なのか。転職支援をしてきた私が転職相談は誰にすべきかを別記事で解説していますので、ぜひご参照ください。
【プロが解説】転職相談はだれにする 転職相談はだれにすべき?
【著者情報】くまさん(介護と転職のアドバイザー)
| 年齢 | 在籍期間 | 在籍企業 |
|---|---|---|
| 22~34歳 | 10年 | 金融機関勤務(大手銀行、米系証券会社) |
| 35~45歳 | 10年 | 大手転職エージェント |
| 45~50歳 | 5年 | 介護系ベンチャー企業 |
| 50歳~ | 5年以上 | 独立して介護と仕事のコンサルタント |
| 年 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1970年 | 0歳 | 神奈川県横浜市に生まれる。 |
| 1992年 | 22歳 | 大学卒業後、みずほ銀行に入行(法人営業担当)。 |
| 2000年 | 30歳 | 米系証券会社に転職し、主に債券を扱うトレーダーを行う。 |
| 2005年 | 35歳 | 大手転職エージェントにキャリアチェンジ(ミドル層の転職支援)。広告やプロモーション全部門の責任者となる。またキャリアアドバイザーとしての経験もあり、求職者のお気持ちに寄り添うカウンセリングを得意とした。 |
| 2015年 | 45歳 | IPO直前の介護ベンチャー企業に転職し、介護事業者の収益改善コンサルティングに従事。特養、訪問介護、通所介護、または有料老人ホームの経営や人事コンサルタント業務を行う。また、一般ユーザー向けには介護の相談窓口サービスを提供し、とくに仕事と介護の両立に悩む会社員をサポートしてきた。 |
| 2020年 | 50歳 | 独立し「Dr.介護と仕事のアドバイザー」として企業制度設計や講演、情報発信を開始。その流れで本ブログを執筆中。現在に至る。 |
| No. | 得意分野 |
|---|---|
| 1 | 介護と仕事の両立支援(一般ユーザー向け) |
| 2 | ミドル・シニア層(30代~50代)のキャリア再構築・転職支援(一般ユーザー向け) |
| 3 | 介護人材の採用・定着(介護事業者向け) |
| 4 | 介護事業者の経営支援(介護事業者向け) |
| 5 | ダイバーシティ経営(介護離職防止)(介護事業者向け) |
| 6 | 施設(老人ホーム)選びのアドバイス(一般ユーザー向け) |
| 7 | 50代以降のキャリア再デザイン(一般ユーザー向け) |
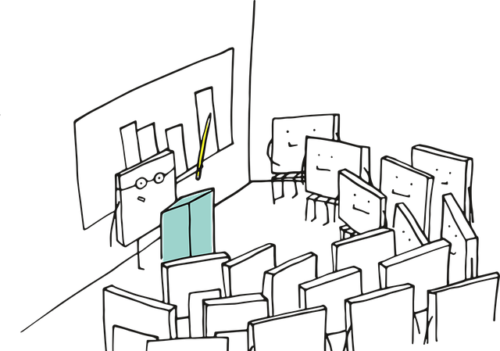


わたしのキャリアは少しユニークで、「金融」「転職エージェント」「介護コンサルタント」と様々な業界を経験してきました。ちょっと変わってますよね(笑)。しかしこの私の変わった経験が、まさしく「仕事と介護の両立」に悩む会社員のみなさんにお役に立てるものと思い、本ブログの執筆を開始しました。
私の勤務していた転職エージェントは大手で、みなさんもよく知っている会社名だと思います。ここではあくまで中立な立場で転職支援をしたいので、社名は伏せさせて頂いています。転職サポートについては、プロ中のプロと自負しておりますので、みなさんのお仕事に関する悩みを解決します。
またその後介護分野への興味が高まり、介護系ベンチャー企業に転職をしました。そこではおもに、特養、訪問介護、通所介護、または有料老人ホームの経営や人事コンサルタント業務を行ってきました。また新規事業として介護に悩む人への相談窓口業務を立ち上げてサービスを提供していました。
このような経験がある私に、仕事と介護のお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に相談をしてみてください。