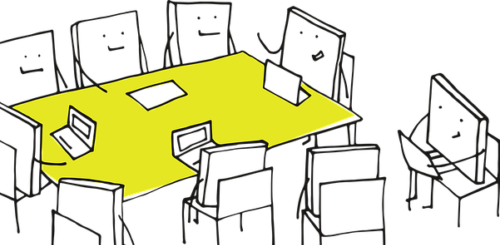最近の父は歩行が不安ですので、介護について考え始めようと思っています。バリアフリーですとか、手すりの設置とか。ただ、まだ介護のことがよく分からなくて、何をするのが一番良いのかが分かっていません。

こんにちは、介護と転職のアドバイザー「くま」です。みなさんほとんどがママ美さんと同じですよ。介護はいきなり直面することも多いので、事前に準備をしている人も少ないのです。それではここで介護サービスの種類について勉強していきましょう。
いよいよ親の介護が必要になったとき、真っ先に頭をよぎるのが、そもそも「介護サービスのことがよく分からない」ということではないでしょうか。
どんな介護サービスがあって、それぞれの介護サービスはどのような特徴があるのか?介護サービスの種類と違いについて、大まかで良いので知っておくことが重要です。それでは介護サービスについて、どこよりも分かりやすく説明して行きます。
介護サービスの種類と一覧
介護サービスとは、介護保険を利用して受けられるサービスの総称です。要支援1~2、または要介護1~5に認定されると、所得に応じて費用の1~3割を自己負担する形で利用できます。
| サービス名 | 対象者 |
|---|---|
| 介護給付サービス | 要介護1~5の認定を受けた人 |
| 介護予防給付サービス | 要支援1~2の認定を受けた人 |
介護サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。これは、市区町村の窓口で申請し、調査員の訪問調査や主治医の意見書をもとに判定されます。

要支援1,2の方はまだ比較的元気な人になります。介護度が増すと(要介護1→5)、お体の調子が悪い方が増えていきます。
介護サービスの種類

くまさん、そろそろ親の介護を真剣に考えないといけないんですが、介護サービスってどんな種類があるんでしょうか?まずは全体像を教えてください。

もちろんです。介護サービスは大きく分けて5つのタイプがあります。今日は順番にご説明しますね。
その1)訪問介護サービス

まずは訪問型介護サービスです。自宅に介護スタッフが来てくれるサービスで主に3種類あります。
| おもなサービス名 | 説明 |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 食事や入浴、排泄介助など日常生活のお手伝いを行うサービス |
| 訪問看護 | 看護師が医療処置や健康管理を行うサービス |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士などが身体機能維持・回復のためのトレーニングを実施するサービス |

外出が難しくなってきている私の親には助かりそうなサービスです。わざわざ自宅に来てくれる介護サービスということですね。
その2)通所介護サービス

次に紹介するのが通所介護サービスです。日帰りで施設に通い、まとまった時間でケアを受けるものです。代表的なものが以下のようなものになります。
| おもなサービス名 | 説明 |
|---|---|
| デイサービス(通所介護) | 食事・入浴、レクリエーション、機能訓練などをまとめて受けられるサービス |
| デイケア(通所リハビリ) | 医療機関併設のリハビリテーション中心サービス。リハビリの専門家と設備が充実している |

なるほど、いろんな方が集まる通いの日帰りの介護サービスということですね。社会的に交流ができるのも魅力かもしれません。
その3)短期滞在型サービス

内容はよく分からないのですが、ショートステイっていうのもありますよね。

はい、ショートステイ(短期入所生活介護)というのは、ご家族が急用や旅行で介護ができない間、数日から数週間、施設に泊まり込みでサポートを受けられるものです。旅行だけでなく、ご家族のひとときの休息や緊急時の受け皿としても活用できますよ。
その4)居住型サービス

このサービスが一般的にみなさんがご存じかもしれません。施設に入居する居住型サービスにはいくつか種類がありますので混乱しがちです。以下の4つを覚えておくとよいでしょう。
| おもなサービス名 | 説明 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的施設で費用が比較的抑えめ。要介護3以上が対象で、生活全般の支援や介護サービスを受けられる |
| グループホーム | 認知症ケアに特化した小規模(9~18人程度)の共同住宅。家庭的な雰囲気で、少人数制のケアと日常動作の支援が特徴 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立~要支援の方が対象。安否確認や生活相談が付帯し、自室での自立生活をメインとする |
| 有料老人ホーム | 介護(介護付)、住宅(住宅型)、健康(健康型)の3タイプがある。設備やサービス内容に応じて費用が変わり、幅広いニーズに対応可能 |
その5)その他の支援サービス

ここまででもけっこう種類がありますね、まだあるんですか?

安心してください、次で終わりです。最後に紹介するのは「その他の介護サービス」です。
| おもなサービス名 | 説明 |
|---|---|
| 福祉用具貸与・販売 | 手すりや車いす、介護ベッドなどを貸与または販売し、ご自宅に設置して使いやすい環境を整える |
| 住宅改修 | 段差解消や手すり取り付けなどを行い、安全な住環境をつくる |
| 地域支援事業 | ボランティアによる見守りや学習支援、地域の自主グループ活動などを提供する |

まとめると、「自宅で受けるサービス」「自宅から通うサービス」「一時的に入居できる短期滞在」、そして「常時入居できる施設」と、いろいろな選択肢があるんですね。

その通りです。まずは親の身体状態やご家族の状況を整理して、どのサービスから試すかを決めると良いですよ。以下に介護サービスの一覧についてまとめておきます。
介護サービスの一覧
| サービス分類 | 具体的なサービス |
|---|---|
| 自宅に訪問 | ・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリ ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
| 施設に通う | ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリ ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
| 訪問・通い・宿泊を組み合わせる | ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
| 短期間の宿泊 | ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 |
| 施設等で生活 | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ・介護医療院 |
| 地域密着型サービス (小規模施設等) |
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
| 福祉用具を使う | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 |
介護サービスを受けるには
それではここから介護サービスを利用するまでの大まかな流れを確認しておきましょう。
要介護認定の申請

そもそも“要介護認定”ってどうやって申請するんでしょう?

要介護認定は、介護保険サービスを使うために必要な認定です。お住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターで申請します。申請書と医師の意見書を提出すると、訪問調査と主治医意見書をもとに担当者が認定を行い、要支援1~要介護5のいずれかに判定されます。結果は1ヵ月ほどで通知されますよ。
- 窓口に相談・申請書提出
住民票のある市区町村(=「保険者」)の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで申請書を受け取ります。申請書に本人・家族の情報、病歴や日常生活での困りごとを記入します。 - 訪問調査
市区町村から派遣された調査員(全国的にはホームヘルパーや看護師等)が自宅を訪問し、身体機能や認知機能、家事動作の状況を約30~60分かけて聞き取り調査します。 - 主治医意見書の提出
かかりつけ医に、日常生活での状況や疾病の状態をまとめてもらい、市区町村に提出します(原則、申請者が医療機関に依頼)。 - 審査・認定
介護認定審査会が調査結果と医師意見書をもとに点数付けし、要支援・要介護の度合い(要支援1~2、要介護1~5)を決定します。 - 認定結果の通知
申請から30日以内に認定結果が「介護保険被保険者証」とともに郵送されます。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成

次はケアプランの作成です。ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)と一緒に作ります。
ケアマネジャーは市区町村や民間の居宅介護支援事業所に所属していて、みなさんとの面談を通じて生活状況や家族の希望をヒアリングします。そして、週何回デイサービスを利用するか、訪問介護をどう組み合わせるかなどを計画書にまとめます。通常、要介護認定の通知から1~2週間でプランが完成します。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)の選定
市区町村に登録された居宅介護支援事業所から、ケアマネジャーを選びます。 - 面談とニーズ把握
ケアマネジャーが自宅を訪問し、本人やご家族の希望・生活環境・予算・医療状況などを詳しくヒアリングします。 - プラン提案
要介護度や本人の状況に応じて、利用可能なサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与など)を組み合わせたプラン案を提示します。 - ケアプランの確定
家族と話し合いながら内容を調整し、最終的な「ケアプラン」を書面で作成します。以後、この計画に沿ってサービスを利用します。
サービス事業者の選定・契約

プランができたら、どの事業者を使うか決めて契約するんですよね?

その通りです。ケアマネからデイサービスや訪問介護などの候補事業者を提案されますので、まずは施設や事業所を見学・体験利用して雰囲気を確認しましょう。気に入った事業者があれば、契約書にサインして利用開始日を決定します。契約手続きはだいたい1~2日で完了しますよ。
- 事業者リストの入手
市区町村のHPやケアマネジャーから、管轄エリアの登録事業者一覧を受け取ります。 - 見学・説明受講
気になるデイサービスや訪問介護事業所を見学し、職員の雰囲気や設備、提供プログラム(レクリエーション内容など)を確認します。 - 利用申込・契約
希望する事業者に「利用申込書」を提出し、サービス利用の契約を締結。利用料金や利用日時、緊急連絡先などを取り決めます。

自宅で出来る介護サービスではなくて、老人ホームを探したいのですが自分で探すことも出来るのですか?場所や費用をいろいろと比較してみたいのですが。

老人ホームを詳しく調べたいときなどは、大きく分けて2つの方法があります。一つは「老人ホーム検索サイト」を利用して探します。「みんなの介護」や「LIFULL介護」に登録して希望の施設を探すことができます。エリアや月額にかかる費用などで検索することができます。もうひとつの方法は「老人ホーム紹介会社」を利用して探す方法です。老人ホーム紹介会社は、対面での相談が可能です。以下に表で違いについてまとめてみました。
| 項目 | 老人ホーム紹介会社 | 老人ホーム検索サイト |
|---|---|---|
| サポートの手厚さ | ◎ 専門相談員が個別に提案・見学同行・手続き代行も可 | △ 施設は自分で探し、資料請求や見学予約は自分で手続きが必要 |
| 情報の範囲 | △ 狭いエリアの提携施設が中心で、全国の施設はカバーしていないことがある | ◎ 全国の施設を比較可能(検索・絞り込み機能あり) |
| 情報の深さ | ◎ 空室・価格交渉・キャンセル情報など、非公開の内部情報も得られる | △ 情報は基本Web上のもの。鮮度にバラつきがある場合も |
| 対応時間 | △ 平日昼間が多く、夜間・土日は相談しにくい | △ 平日が多く、土日は相談しにくい |
| 体験談・口コミの有無 | △ 担当者に直接聞けるが、件数は少なめ | ◎ 利用者の口コミが多数掲載されていて、比較材料が多い |
| 専門スタッフとの相談 | ◎ ケアマネ・福祉士などが親身に対応 | ○ アドバイザーに電話相談できる機能があるが、相談者のキャリアはバラツキが多い |
| 担当者の質のばらつき | △ 経験や相性で提案の質に差が出ることがある | △ 経験や相性で提案の質に差が出ることがある |
利用開始前の準備

いよいよ利用開始ですね。何を準備すればいいでしょう?
- サービス担当者会議
ケアマネジャー、サービス事業者、家族、場合によっては医師も交えて会議を行い、ケアプランの共有と連携体制を確認します。 - 事前訪問・トライアル
初回利用前にホームヘルパーやドライバーが自宅や施設を訪問し、本人の好みや生活リズムを把握します(訪問介護やデイサービス)。 - 福祉用具・住宅改修の手配
必要に応じ、ケアマネジャーの支援で福祉用具(介護ベッド、手すりなど)のレンタル手続きを行ったり、住宅改修の見積もり・工事を依頼します。
介護サービスの利用開始
- 定期的なサービス提供
訪問介護なら週数回、デイサービスなら週1~数回など、ケアプランに沿った頻度でサービスが実施されます。 - モニタリング・プランの見直し
ケアマネジャーが定期的(原則1か月に1回)に訪問し、利用状況や本人・家族の満足度、身体状態の変化を確認。必要があればケアプランを変更します。 - 要介護度の更新手続き
6か月ごと(または状態が急変したとき)に再度、要介護認定の更新申請を行い、サービス内容や利用上限枠を調整します。

以上のステップを踏むことで、介護保険を活用した各種サービスをスムーズに利用開始できます。疑問点や困りごとは、まずは地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口、あるいは担当ケアマネジャーへ相談しましょう。
介護保険とは?概要と仕組み

ここで介護サービスを受ける前に、介護保険の仕組みについても勉強しておきましょう。
介護保険は、日本が2000年に導入した社会保険制度で、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人が保険料を負担し、介護が必要になった際に介護サービスを利用できます。
被保険者の分類
被保険者は年齢によって以下の2つに分けられます:
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 第1号被保険者(65歳以上) | 原因を問わず要介護状態になった場合に利用可能 |
| 第2号被保険者(40~64歳) | 特定疾病(例:がん、糖尿病性腎症など)が原因で要介護状態になった場合に利用可能 |
介護保険の申請から利用まで
介護保険を利用するためには以下のステップを踏む必要があります:
1. 要介護認定の申請
親の住所地の市区町村で要介護認定を申請します。必要書類は以下の通り:
| 年齢区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 65歳以上 | 介護保険被保険者証 |
| 40~64歳 | 医療保険証 |
| 全対象(事前) | 主治医の意見書(事前準備が必要) |
2. 認定調査
・認定調査員が本人の生活状況を確認します。家族が同席して状況を補足説明すると、適切な結果が得られやすくなります。
3. ケアプランの作成
・要介護度が認定されたら、ケアマネジャーと相談し、ケアプランを作成します。利用したいサービスや日常の困りごとを具体的に伝えることがポイントです。
4. サービス利用開始
・ケアプランに基づいて介護サービスの利用を開始します。事業者と契約を結び、支援が始まります。
介護保険のメリットと注意点
メリット
・費用の軽減:介護保険が適用されるため、費用の1~3割の自己負担で利用可能。
・豊富な選択肢:多様なサービスから選択可能で、個々のニーズに応じた利用ができる。
・地域密着型サポート:市区町村単位で提供されるため、地域特性に応じた支援を受けられる。
注意点
・費用負担:要介護度やサービス内容によって自己負担額が異なる。
・手続きの煩雑さ:認定申請から利用開始までに時間がかかる。
・サービスの制限:介護保険が適用されないサービスもある。
介護保険を上手に活用するためのポイント
早めの相談と準備
・介護が必要になる兆候が現れたら、早めに地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。
サービスの併用
・デイサービスや訪問介護を組み合わせることで、介護者の負担を軽減できます。
自分の健康を守る
・介護者自身の健康維持も重要です。定期的にリフレッシュできる環境を整えましょう。
介護保険は、高齢者の生活を支える重要な制度です。親や家族が介護を必要とする状況になったとき、早めの情報収集と準備が鍵となります。この記事を参考に、介護保険制度を上手に活用し、仕事と介護を両立しながら安心した生活を送れる環境を整えましょう。
信頼できる介護サービスの探し方
ケアマネジャーへの相談
・介護支援専門員(ケアマネジャー)は地域の事業所情報に精通しています。要介護度やご家族のライフスタイルに合った候補を複数挙げてもらい、比較検討しましょう。
事業所の見学・面談
・実際に施設や訪問スタッフを見て、雰囲気や人柄を確かめます。事前に見学予約し、サービス内容・スケジュール・費用の説明を受けた上で、疑問点はその場で解消しましょう。
利用者・家族の口コミ・評判チェック
・インターネットの口コミサイトや地域包括支援センターに寄せられる声を参考に、スタッフ対応やトラブル対応の実績を確認。同じ市区町村内で利用した知人・友人の生の声も貴重です。
スタッフの資格・研修状況の確認
・介護福祉士、看護師、社会福祉士など有資格者の在籍比率や、定期的な研修実施状況をチェック。スタッフの定着率(勤続年数)が高い事業所は、サービスの質が安定しやすい傾向があります。
費用の透明性と契約条件
・介護保険適用後の自己負担額(原則1割または2割・3割)を明示しているか。
追加サービスの料金表やキャンセル料、契約期間・解約条件などがわかりやすく提示されているか確認しましょう。
トライアル利用・契約前確認
・短期トライアル(1日体験、訪問介護のお試し利用など)が可能かどうかを確認。体験後にフィードバックを得て、家族も交えた最終判断を行います。
継続的な評価・見直し体制
・ケアマネジャーや事業所と定期的な「サービス担当者会議」を実施できるか。利用開始後も、本人・家族の満足度や身体状況の変化に応じたプラン見直しのサポートが整っているか確認しましょう。

介護サービスには、訪問介護や通所サービス、施設サービスなど多岐にわたる種類があります。働きながら介護をする人や介護離職を考えている人は、早めに要介護認定を受け、適切なサービスを利用することが重要です。また、信頼できる情報源を活用し、自分や家族に合った介護方法を選びましょう。
まとめ
介護サービスには、訪問介護や通所サービス、施設サービスなど多岐にわたる種類があります。
働きながら介護をする人や介護離職を考えている人は、早めに要介護認定を受け、適切なサービスを利用することが重要です。また、信頼できる情報源を活用し、自分や家族に合った介護方法を選びましょう。

本記事でご紹介した各種サービスや制度のポイントは、知っているだけで準備の「質」と「スピード」が大きく変わる点です。介護は段階的にニーズが変化するため、最初のサービス選択がその後の負担軽減に直結します。働きながら介護を続けるビジネスケアラーの皆さんには、早めの要介護認定申請、ケアマネジャーとの密なコミュニケーション、そして定期的なプラン見直しを強くおすすめします。まずはこの記事でご自身の状況と制度を整理し、次の一歩を踏み出す自信をつけていただければ幸いです。
【著者情報】くまさん(介護と転職のアドバイザー)
| 年 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1970年 | 0歳 | 神奈川県横浜市に生まれる。 |
| 1992年 | 22歳 | 大学卒業後、みずほ銀行に入行(法人営業担当)。 |
| 2000年 | 30歳 | 米系証券会社に転職し、主に株式・為替を扱うトレーダーを行う。 |
| 2005年 | 35歳 | 大手転職エージェントにキャリアチェンジ(国内大手→外資系大手を経験)。キャリアアドバイザーとして求職者のお気持ちに寄り添うカウンセリングを得意とした(ミドル層の転職支援)。 |
| 2015年 | 45歳 | IPO直前の介護ベンチャー企業に転職し、介護事業者の収益改善コンサルティングに従事。有料老人ホームの経営や人事コンサルタント業務を行う。また、一般ユーザー向けには介護の相談窓口サービスを提供し、とくに仕事と介護の両立に悩む会社員をサポートしてきた。 |
| 2020年 | 50歳 | 独立し「Dr.介護と仕事のアドバイザー」として企業制度設計や講演、情報発信を開始。その流れで本ブログを執筆中。現在に至る。 |
| No. | 得意分野 |
|---|---|
| 1 | 介護と仕事の両立支援(一般ユーザー向け) |
| 2 | ミドル・シニア層(30代~50代)のキャリア再構築・転職支援(一般ユーザー向け) |
| 3 | 介護人材の採用・定着(介護事業者向け) |
| 4 | 介護事業者の経営支援(介護事業者向け) |
| 5 | ダイバーシティ経営(介護離職防止)(介護事業者向け) |
| 6 | 施設(老人ホーム)選びのアドバイス(一般ユーザー向け) |
| 7 | 50代以降のキャリア再デザイン(一般ユーザー向け) |