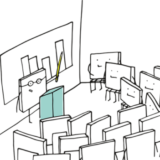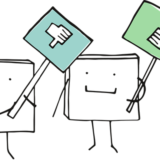仕事と介護をしている会社員、いわゆる「ビジネスケアラー」が増加してきており、2025年には300万人を突破したとも言われています。
急に介護が必要になったとき、仕事との両立をどう乗り越えればよいか、不安に思う人も多いと思われます。
本記事では、仕事と介護を両立するための実践的な方法や役立つ制度、さらには両立を成功させるためのヒントを詳しく解説します。
 Dr.キャリアと介護のアドバイザー
Dr.キャリアと介護のアドバイザー
ビジネスケアラーとは
ビジネスケアラーとは、仕事をしながら家族や親族を介護する人のことを指します。近年、共働き世帯や独身世帯の増加、少子高齢化に伴い、仕事と介護の両立が社会的な課題となっています。さらに、親の介護に加え、複数の家族を同時に介護する「多重介護」や、子育てと介護を同時に行う「ダブルケア」に直面するケースも増えています。
現状とデータ
| ビジネスケアラーの数(2025年予測) | 約307万人 |
| 多い年齢層①(55–59歳) | 約63.8万人 |
| 多い年齢層②(50–54歳) | 約53.8万人 |
 Dr.キャリアと介護のアドバイザー
Dr.キャリアと介護のアドバイザー
家族にケアが必要になる兆候
家族が要介護状態になる可能性を見極めるには、フレイル(心身機能の低下)やロコモティブシンドローム(運動器の障害)に注意が必要です。ぜひこのふたつの言葉は覚えておいて、その内容を調べてみてください。
【出典:NPO法人となりのかいご「不安解消チェックシート」】
介護と仕事を両立している人の現状
介護と仕事の両立率は約6割
総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると、約365万人が介護と仕事を両立している一方、年間約10万人が介護離職をしています。特に55~59歳の年齢層で離職率が高いのが現状です。
・理由:責任あるポジションに就いている管理職などが、介護との両立に困難を感じるケースが多い。
・影響:離職後の収入減、精神的孤立、再就職の難しさが主な課題となっています。
ビジネスケアラーの、仕事と介護の両立がうまく出来るようになった実例
ビジネスケアラーにとって、仕事と介護のバランスを取ることは大きな課題です。ここでは、実際に支援策を活用して両立を成功させたビジネスパーソンの事例をご紹介します。
■事例:山田さん(仮名)のケース
山田さん(42歳)は、大手製造業に勤務するプロジェクトマネージャーです。妻が進行性の認知症と診断され、日常生活の支援が必要となりました。仕事の責任も重く、家庭での介護だけでは対応が難しいと感じていた山田さんは、以下の支援策を活用することで、仕事と介護の両立を実現しました。
また山田さんは、企業が提供する介護休業制度を活用し、必要な時に柔軟に休暇を取得できるようにしました。これにより、急な介護の必要性にも対応できるようになりました。
在宅介護サービスの導入 デイサービスや訪問介護サービスを利用することで、妻のケアを専門家に任せる時間を確保。これにより、山田さんは安心して仕事に集中できる環境を整えました。
地域包括支援センターのサポート 地域包括支援センターの相談窓口を活用し、介護に関する情報収集や支援プランの作成を行いました。専門家からのアドバイスを受けることで、効果的な介護方法を学びました。
家族や友人のサポート 山田さんは、家族や友人に協力を依頼し、定期的なケアの分担を行うことで、負担を軽減しました。
<結果>
これらの支援策を活用することで、山田さんは仕事と介護のバランスを保ちながら、妻のケアも充実させることができました。企業の理解と地域の支援が大きな助けとなり、山田さんはストレスを軽減し、職場でのパフォーマンスも維持することができました。
 Dr.キャリアと介護のアドバイザー
Dr.キャリアと介護のアドバイザー
| 介護休暇 | 介護休業 | |
| 目的・定義 | 通院の付き添いなど、短時間の家族介護を行うための休暇 | 要介護状態の家族を介護するための長期的な休業 |
| 対象家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 | 同左 |
| 取得可能日数/回数 | ・対象家族1人:年5日まで ・2人以上:年10日まで |
対象家族1人につき通算93日まで(3回まで分割取得可) |
| 休暇中の賃金 | 有給/無給は会社規定による | 原則無給 |
介護離職のデメリット
介護離職は家族や本人に大きな影響を及ぼします。以下は、主なデメリットです。
1. 収入の減少
介護離職により、定期的な収入源が途絶えます。
・影響:生活費や介護費用の自己負担増加、退職金や年金額の減少が老後に響く。
2. 再就職の難しさ
介護が落ち着いた後も、再就職は容易ではありません。
・年齢の壁:年齢が高いほど、正規雇用への復帰が難しくなる。
・非正規雇用:パートや契約社員として働き始めるケースが多い。
3. 心身の負担の増加
介護に専念することで身体的・精神的負担が増えます。
・身体的負担:腰痛や睡眠不足の発生。
・精神的負担:社会的孤立感やストレスの蓄積。
在宅介護と仕事の両立の課題
1. 仕事と介護の両立の難しさ
・急な家族のケアが必要になり、仕事を中断せざるを得ないケース。
・在宅勤務中でも介護の合間に仕事を続けることが困難。
2. 心身の負担
・食事、排泄、入浴といった日常的なケアによる体力消耗。
・夜間のトイレ介助や見守りが睡眠不足を引き起こす。
3. 経済的な負担
介護保険制度を活用しても、サービス利用時間外や保険適用外の費用が発生することが多い。これにより、介護者の経済的な負担が大きくなります。
4. 介護離職のリスク
介護のために仕事を辞めると、以下のような事に直面する可能性があります。
・精神的な孤立感
・再就職の難しさ
・家庭の経済的困窮
厚生労働省の調査では、介護離職者の精神的負担が増加したと回答した人が56.3%に上りました。
【出典:厚生労働省「令和元年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握調査」】
国の支援策
1. 介護休業制度
・対象:要介護状態の家族1人につき通算93日まで。
・分割取得:最大3回まで分割可能。
・申請方法:勤務先へ申請。
【出典:厚生労働省「介護休業制度特設サイト」
2. 介護休暇制度
・短期間の休暇:年間5日(複数の対象者がいる場合は10日)。
・給与の支払い:会社の規定により異なる。
3. 介護休業給付金
・支給額:賃金の67%。
・申請先:勤務先経由でハローワーク。
4. 時間外労働・深夜労働の制限
・深夜業の制限:22時—5時の勤務免除を申請可能。
・時間外労働の制限:1か月24時間、1年150時間以内に制限。
両立するための方法
1. 相談先を知る
・地域包括支援センターや自治体窓口に相談し、要介護認定を受けることが重要です。
【出典:厚生労働省「仕事と介護の両立支援ガイド」】
2. 家族と早めに話し合う
・誰が主な介護者になるか。
・介護費用の分担方法。
3. 職場に状況を伝える
・早期の周知で職場の理解を得る。
・介護休暇や短時間勤務制度を活用。
4. 外部のサポートを活用
・保険適用外サービスや介護施設の利用。
・ケアマネジャーに相談し、最適なケアプランを作成。
まとめ
ビジネスケアラーの課題は、個人だけで解決できるものではありません。
国や企業の支援策を活用し、職場や家族と連携しながら取り組むことが重要です。早めの相談と計画的な準備が、仕事と介護の両立を可能にします。
関連リンク